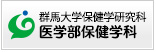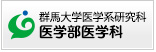あいさつ
WHOCCホームページ挨拶

群馬大学長
石崎 泰樹
現代の医療は高度化と専門化が進み、患者さんのケアに当たっては、医師、看護師をはじめとして多くの職種の医療人が関わるようになっています。多様な分野でのプロフェッショナルであるこれらの医療人が相互に連絡をとりながら上手に役割を分担し、患者さん一人一人にとって最適の医療をデザインすることが必要です。
群馬大学大学院保健学研究科・医学部保健学科では、設置当初から、看護師、保健師、助産師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士など個々の医療人材養成の枠を越えて、多職種の医療人連携による医療、すなわちチーム医療の重要性に着目し、研究と人材育成を行ってきました。医師を養成する医学部医学科との密接な連携のもとに、学部段階から将来のチーム医療を見据えて同じクラスで学ぶ機会を取り入れたカリキュラムも行っています。このような本学の取組は、文部科学省のGP事業「多専攻学生による模擬体験型チーム医療実習」(2007年~2009年)、「総合的学士力の育成に向けたチーム医療教育」 (2010年~2012年)にも選定されて、チーム医療教育の充実を図るとともに様々な経験と実績を積み重ねてきました。
チーム医療体制を推進する過程では、日本インタープロフェッショナル教育機関ネットワーク(Japan Interprofessional Working and Education Network: JIPWEN)を組織するなど、様々な取組を通じて他大学との連携強化を図っています。さらに、モンゴルにおけるリハビリテーション教育プログラムの立ち上げなど、アジアにおける医療人材育成にも努めています。この間、WHOへの人材派遣や交流を通じ、グローバルレベルでの医療人養成とチーム医療の推進について実践を積んできました。
インターネットの発達により、世界中で情報が共有される時代にあって、グローバルな視野のもとにWHOコラボレーションセンターが本学に設置されました。これからの医療の形である多職種の医療人連携を推進するこのセンターが、日本やアジアをはじめとする世界の方々との共同作業で、チーム医療を担う医療人の育成に大きな成果を挙げることを期待しています。
多職種連携教育研究研修センター長からのご挨拶
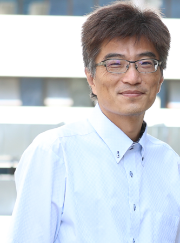
多職種連携教育研究
研修センター長
李範爽(Bumsuk LEE)
本センターは2013年にWHO協力センターに指定されました。それ以来、WHOとJICA、JIPWEN大学を始めとする多くの国際機関や教育機関と連携しながら、毎年8月にIPE Training Courseを開催、共同研究を実施し、国際ネットワーク構築などさまざまな活動に取り組んできました。微力ながらIPEの世界普及に貢献できたと自負しています。
これまでの活動に加え、2025年から2029年の間は以下の活動に重点的に取り組んでいく所存です。
- 卒後IPEのキー・コンピテンシーの確立とその教育コンテンツの開発と普及
- 世界共通価値に基づいた保健医療介護連携モデルの開発と普及
- IPEとCP(Collaborative Practice、多職種連携)が保健医療介護人材の心理的安全性に及ぼす影響の検証
- IPE国際学生組織の創設・発展の支援
働く側とサービスを受ける側という2つの視点から、IPEとCPが個人と組織、社会の幸福に及ぼす正の影響を学術的に検証し、その成果を人類共通の知として広めることが本センターの社会的使命であると考えています。本センターの更なる発展のために、微力ながら一生懸命取り組んで参ります。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
コーディネーター特別教授からのご挨拶

群馬大学がWHO協力センター(多職種連携教育研究センター: WHO Collaborating Centre for Research and Training on Interprofessional Education)認定を受けて早8年がたちます。5年前に、このWHO協力センターの強化する為に、世界保健機関(WHO/SEARO)から群馬大学に呼ばれ、当初多職種連携教育の内容を十分理解できず仕事をお引き受け致しましたが、多職種連携教育の重要さをすぐに認識致しました。この多職種連携教育を専門として活動しているWHO協力センターは、残念ながらまだ群馬大学を含め世界で2機関(2か国)しかなく、本学のより一層の活躍が必要です。近年はWHO本部患者安全部門より、当WHO協力センターの活動である多職種連携教育との連携強化を要請され、「世界患者安全デー(World Patient Safety Day)」に参加し、WHO本部、WHO/WPRO(西太平洋地域事務局)、厚生労働省、及び関係諸機関から高い評価を受けております。
WHOは国際機関な為に、世界中から宗教・人種・文化の異なる人々がいろんな職種のエクスパートとして集まっています。SEAROでは、全職員を半分2回に分けて3日間電波が届かない郊外のリゾートで「リトリート」と称して、職種連携教育を行い、より良い仕事が協力して行えるよう心がけております。これからも多職種連携教育の重要性が増えており当WHO協力センターの活躍が期待されています。
WHO協力センター 顧問としてのご挨拶

WHOは世界的な保健人材不足に対するグローバル戦略の中の一環として、また社会の要請に応える21世紀型の保健医療人材教育として多職種連携教育(IPE)の普及と充実を重要な課題と位置付けています。群馬大学はIPEの教育実績、研究成果をもって2013年にWHO Collaborating Centre (WHO CC)に指定され積極的に活動を行ってきました。現在、本分野のWHO CCは南アフリカ共和国の1施設と私たちの2施設のみです。
活動内容は、IPE関連の国際会議、学術集会への参加や国際シンポジウムの開催による普及活動、IPEの教育効果の検証による論文報告(研究)、国外教育機関、特にアジア地域におけるIPEの導入支援を目的とした定期的なトレーニングコースの開設と現地でのワークショップの開催です。これまでWHOの支援の下、大韓民国、モンゴル、中華人民共和国、ベトナム社会主義共和国、タイ王国、カンボジア王国、ラオス人民民主共和国、フィリピン共和国、インドネシア共和国、ネパール連邦民主共和国、トルコ共和国、等のお国の人々がIPE導入に高い関心をもって参加しています。参加された多くの国ではすでにIPEの実施と成果の解析や報告がなされるようになりました。本学のIPEの成果も多くの英文論文として報告しています。本websiteで公開しておりますのでご覧いただければ幸いです。
私は、2020年3月に群馬大学を退任して高崎健康福祉大学に異動しました。後任のWHO CCのHead(群馬大学多職種連携教育研究研修センター長)は篠﨑博光教授が務めており、私は顧問として微力ながらセンターの発展に寄与したいと考えています。個人的には医療安全の分野の多職種連携マインドは学部教育で育成することが大切と考えているところです。最後に、IPE教育とWHO CCのさらなる発展を祈念するとともに、皆様方のご支援を賜りますようどうぞよろしくお願いいたします。